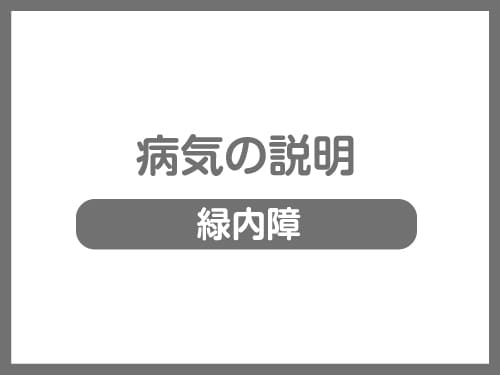
前回の続きです。
前回は高齢者の緑内障診療においての検査に対する、考察でしたが、今回は治療について。
高齢者における治療の主体は、薬物治療です。
国内のレセプトデータから治療継続率が調査できますが、それによりますと、主治医が思っている以上に、緑内障患者さんは、継続率が悪いということがわかています。
治療継続率は、点眼開始後3か月後 72%、1年後 61%まで低下している。
以前このことは、ブログで書いたことがありますが、主治医の実感以上に悪い とわざわざ書かれていますから、自分の患者さんは大丈夫と思っているのですが、ドロップアウトしてしまう患者さんが大分いるのは事実のようです。
また点眼そのものが高齢者には、難しかったり失念してしまったりということですが、最近はスマホアプリで点眼支援や管理に特化したものがあり、今後はスマホを使いこなせる高齢者が増えることにより、手帳に書く カレンダーにつける といった古典的な方法に追加的に活用が望まれる。
点眼のしやすさという点では、座っての点眼より、横たわっての点眼の方が成功率が高い。
真夏の室温が高い時期を除いて、私もベッドサイドに点眼薬を置いておいて、朝起き出す前につけることを勧めたりしています。
冷暗所保存が多い緑内障点眼薬ですが、全然させないより点眼回数が確保できるのであれば、それも一考に値すると思います。
高齢緑内障患者さん特有の課題として、約8割の患者さんが緑内障以外の慢性疾患を併発しており、生活習慣病に比べて社会的な認知度が低いうえに、自覚症状が乏しい緑内障の治療優先順位が低くならないかが懸念される と書かれています。
更に80代半ば以降の高齢者の認知症の発症率は4割を超えると推測されているそうで、点眼薬治療の大きなハードルとなる となっています。
私が患者さんを診ている実感とは、少し違いますが、開業医は大学の専門医と違い、緑内障患者さんは80代から点眼開始になる人よりも、早ければ40代多くは50~60代から点眼開始となっている患者さんが多いため、しっかり習慣化している方も多いです。
つまりそれまでの治療傾向が大切で、あまり勤勉にさせていなかった場合、点眼の習慣化もできていないため、それがドロップアウトの原因にもなると思います。そうならないように、やさしくでもきっぱりと点眼を促すことは大切だと思います。
私の印象では、むしろ働き盛りの中年世代より、きっちりさせている印象です。
ただコロナ禍の影響として、パンデミック後点眼ができなくなっている人が増加しているというデータが海外で報告されているということです。
確かにあの頃は、高齢者は外出を控えるようにといわれていたのですから、独居の患者さんは、薬を手に入れる手立てはなかったという方もいると思います。
色々なことが影響するのですが、医療者としては、例えば患者さん自身が来院できなくても、眼圧を計らないとお薬は出せない と杓子定規な態度でいるよりは、ともかく点眼薬を患者さんのもとに届けるということを、大切にするべきなのだと思いました。





